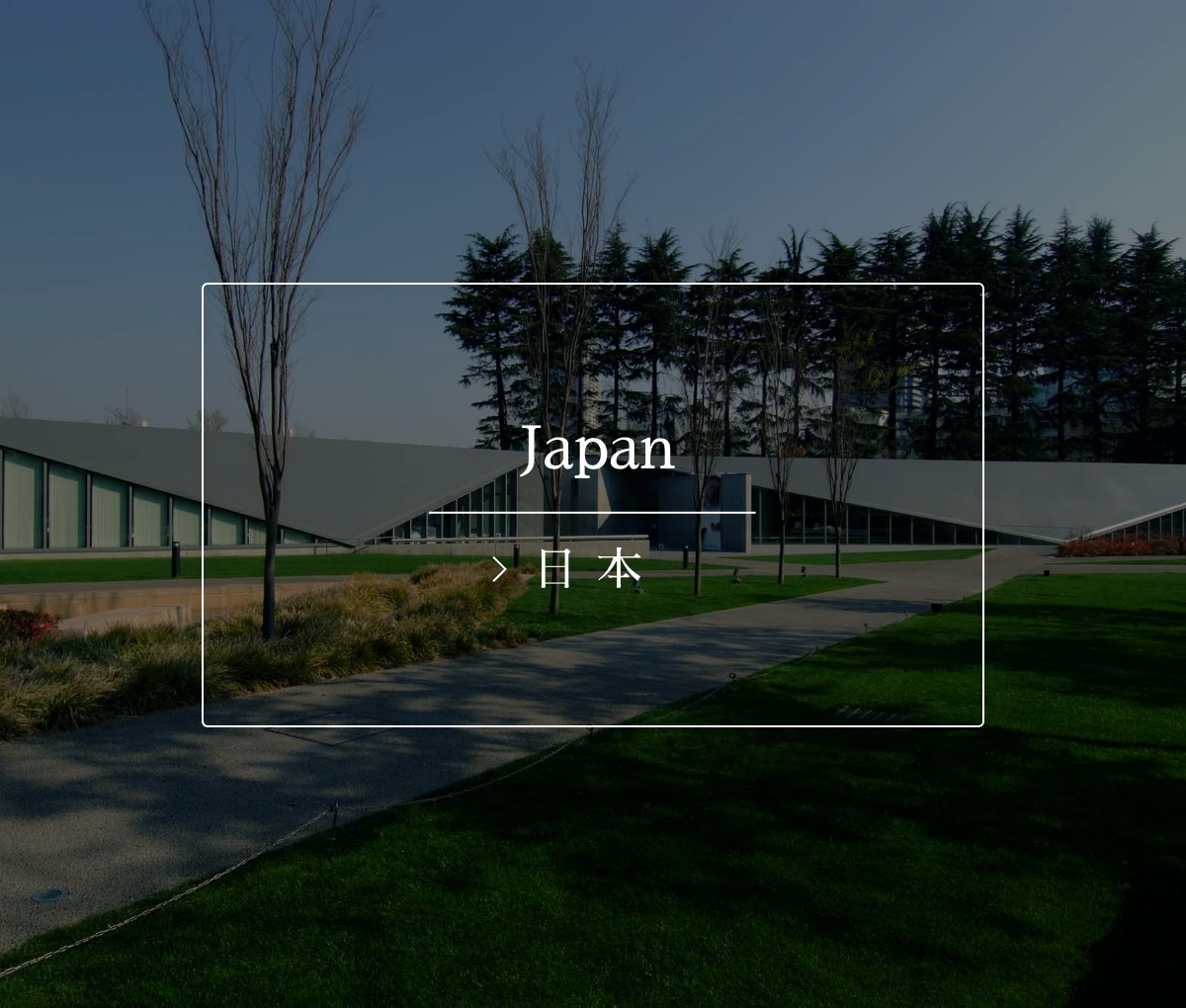建築史の世界へようこそ
建物には「物語」があります。
それは、誰が、なぜ、どんな思いで建てたのか──という人間の営みの記録でもあり、時代の思想や技術が刻まれた“時間の器”でもあります。
「旅行先で見かけた建物がなんだか素敵だった」「マイホームづくりで建築に興味を持った」
そんなきっかけから、建築の世界に足を踏み入れる方も多いはず。
このページでは、これから建築を学んでみたいという方のために、「建築史ってどうやって学ぶの?」「どんなジャンルがあるの?」という疑問に答えながら、建築史の全体像をご紹介します。
Contents
建築史を学ぶ意味とは?
建築は、ただの「形」ではありません。
その背後には、社会・宗教・政治・暮らしなど、時代の背景が深く関わっています。
たとえば、なぜ教会は高くそびえる尖塔を持っているのか?
なぜ日本の古民家は軒先が深くて、木と紙でできているのか?
そうした問いに向き合うことは、デザインの理由を知るだけでなく、「建物を見る目」を持つことにつながります。
建築史を学ぶと、観光で立ち寄る建築物の見方が変わります。
ただの“写真スポット”ではなく、「意味をもって存在している空間」として見えてくるのです。
建築史の5つの主要分類
建築の歴史は、地域や文化、技術の進化によってさまざまに枝分かれしています。
ここでは、これから学ぶうえでの大まかな「地図」となる、5つの分類をご紹介します。
1. 西洋建築史
古代ギリシャ・ローマから始まり、ロマネスク、ゴシック、ルネサンス、バロックなど、教会や宮殿を中心に展開してきた西洋建築の流れです。
「柱のデザイン」や「ドームの構造」など、西洋的な美意識と技術の変遷が読み取れます。
2. 日本建築史
法隆寺に代表される仏教建築から、京都の町家、数寄屋造り、そして江戸〜明治の町並みへ。
日本の建築は、「自然との調和」や「素材の活かし方」が特徴的です。
瓦屋根、障子、縁側など、私たちの暮らしと結びついた建築文化を持っています。
3. 東洋建築史(中国・韓国など)
中国の宮殿建築(故宮など)や、韓国の伝統家屋「韓屋」など、日本との比較で見ると面白さが際立ちます。
たとえば、同じ木造建築でも、構造・色彩・装飾の思想に違いがあります。
4. 近代建築史(19〜20世紀初頭)
産業革命を背景に、鉄やガラスが建築に導入され、建物の構造やスケールに革命が起きました。
エッフェル塔やロンドンのクリスタルパレスに見られるように、「見せる構造」「新素材の活用」が特徴です。
5. 現代建築史(20世紀中盤〜現在)
モダニズム、ポストモダン、デコンストラクティビズム、そして持続可能な建築(サステナブルデザイン)へ。
ル・コルビュジエ、フランク・ロイド・ライト、ザハ・ハディドなど、建築家の個性が強く反映される時代です。
建築史の見どころとは?
建築史を学ぶとき、ぜひ注目してほしいのは以下の3つの視点です。
- 時代の背景
その建物がつくられた時代に、どんな社会や価値観があったか? - 技術と素材
使われた技術や素材の変化が、デザインや構造にどう影響したか? - 人間の営み
その空間で人はどう過ごしたのか?何を感じ、どんな行動をしたのか?
これらを意識して見ていくと、建物が「語りはじめる」ように感じられるはずです。
このサイトでの建築史の学び方
「おとなの建築学科」では、建築史を難しく語りすぎず、けれども深く学べるように以下の工夫をしています。
- 各時代・地域ごとの入門記事
→ 「まずはここから」的に全体像をつかめる内容 - 代表的な建築物とその意味の解説
→ 実際に訪れることができる建築も多数紹介 - 用語・構造・人物のやさしい説明
→ 例えば「ゴシック建築ってなに?」を専門用語ナシでもわかるように - 旅や住宅購入にも役立つ“見方”の紹介
→ 「この建物のどこに注目すると面白いか」が分かるような視点の提供
まずは“建築史の旅”に出かけよう
建築史は、過去の話ではありません。
今、あなたが住んでいる家、通っている駅、訪れたことのある寺や教会、どれもが建築史の一部です。
このサイトでは、そんな“気づかなかった建築の面白さ”を、わかりやすく・丁寧に紹介していきます。
難しそうだと思っていた建築史が、実は日常をもっと豊かにするヒントだったと気づいてもらえたら嬉しいです。